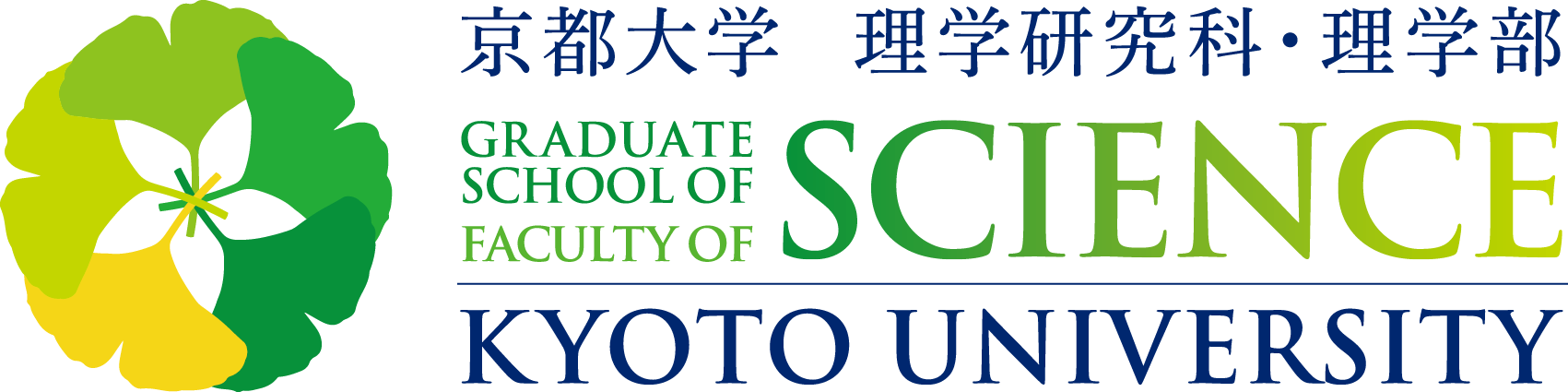米グーグルの創業者らが設立した科学賞「ブレークスルー賞」の今年の受賞者4月5日に発表され、大型ハドロン衝突型加速器(Large Hadron Collider: LHC)を使って素粒子の性質などを調べた4つの国際実験コラボレーション(ATLAS実験、CMS実験、ALICE実験、LHCb実験)に対し、今年度の基礎物理学賞が与えられました。
京都大学が参加するATLAS実験ではLHCの第2期運転期 (2015-2018) において、ヒッグス粒子の精密測定による素粒子質量の起源の解明をはじめ、暗黒物質、超対称性、余剰次元といった高エネルギーで発現が期待される物理現象の探索を強力に推し進め、基礎物理学の限界を前例のない領域まで押し広げました。
京都大学からは理学研究科物理学・宇宙物理専攻から当該期間において学生・スタッフ約20名がATLAS実験に参加し、検出器の運転とアップグレードで大きく貢献したほか、データ解析においてはヒッグス粒子の第3世代フェルミオンとの結合の発見や、超対称性粒子探索をはじめとする数々の重要プロジェクトで主力を担いました。現在進行中の第3期運転期 (2022-2026) や、後継の加速器実験であるHL-LHC (2030-2042)に向けた準備研究においても、引き続き現場の最前線で活躍を続けています。
ATLAS実験京都グループを率いる陳詩遠准教授のコメント「科学がチームプレーの時代になって久しいですが、世界中から1万人以上が参加するLHC実験はその営みの極致的な到達点の一つだと思います。この度我々がチームとして成し遂げたことを評価する形で賞が与えられたことをとても嬉しく思います。」
LHC第2期運転期に超対称性粒子探索で主力を担った三野裕哉特別研究員(現東京大学所属・当時京都大学大学院生)のコメント「LHCだからこそ可能な挑戦として、暗黒物質の起源に迫る超対称性粒子の探索に取り組みました。LHCでしか到達できない領域を切り拓いた今回の成果が、今後の暗黒物質の正体解明に向けた重要な一歩となることを期待しています。」
大学院生・河本地弘氏のコメント:「第2期運転期で得られた多くの知見を元に、LHCの実験現場で運転効率の最大化に努めてきました。超対称性粒子の探索などLHCでしか到達できない未探索の物理はまだまだ残っており、現在取得中のデータを増強してますます強力に探索を推し進め、素粒子物理学や先端技術の発展に資する研究に邁進したいと思います。」
大学院生・辻川吉明氏のコメント: 「様々なテーマの物理研究が可能であるLHCを用いた加速器実験にはまだまだロマンが詰まっています。この受賞を契機に、素粒子実験分野が更に盛り上がっていく未来を期待しています。私個人としましても、この分野のさらなる発展に貢献できるよう研究に邁進してまいります。」